AIが考えた企業ビジョン
2025.03.18
ここ数週間、提案書や企画書、エントリーシートを量産しまくっています。数えたら10日間で重量級の提案書を15本書いていました笑
最近のぼくの提案書の書き方は完全にchat-GPTとの共同作業です。
AIを使えば5,000字の提案書が1時間くらいで書けてしまいます。で、それがまた破壊力があってちゃんと先方に刺さるんですよね。
大まかな作業フローはこんな感じです。
登場する企業や人物の情報をまずインプット
(提案先やMEETSHOPの情報)↓
それ以外の情報をリサーチさせる
↓
提案の大まかなプロットをインプット
(プロットは西尾が手打ちで書く)↓
先方&こちらの動機の言語化をインプット
(これも西尾が手打ちで書く)↓
フォーマットに従って提案書をchat-GPTが書く
(課題→解決策→他の選択肢→その解決法でなければいけない理由、という流れ)
↓
chat-GPTが書いたものを西尾が修正&再びインプット
↓
chat-GPT版と西尾版の違いを言語化してインプット
↓
繰り返し
コツは、、、
骨組みをこちら側が提供することと、こちら側のクセ?指向?をいちいちインプットし直すことですかね。
この作業を挟むようになってからchat-GPTのアウトプット精度がずいぶんとあがったような気がします。

で、、、
なんでこんな話をしているかって言うと、、、
Chat-GPTが勝手にまとめた提案書のなかに「MEETSHOPのビジョンは〜」という記述があったんです。
つまり読み込んだいろんな情報をもとに「MEETSHOPという会社のビジョンはこうであるに違いない」ってchat-GPTが勝手に書いたんです。
(読み込んだ情報のなかには、いろんな企業へのいろんな提案書をpptxファイルにして読み込ませたものが多数あります)
(おそらくはその提案書群からビジョンを考えやがったのだと推測)
Chat-GPTによると、
◎人の行動変容を促し、より健康的な選択肢を増やす
が、MEETSHOPのビジョンらしいですよ笑
最初は「なに勝手に言っとるねん」っておもったんですが、、、、
考えてみたらこれ「けっこういいな」と思い始めています笑

行動変容って言葉はいささかヘルスケア的ではありますが、考えてみたら僕らの会社がやっていることはまさに「行動変容を促す」ことばかりです。
例えば、、、
僕らが企業さんに提案して、で、新規事業が前に進みそうになったら必ず相手に対して伝えることがあります。
相手が大手企業さんだろうと何だろうと必ず伝えます。
それは、
「こちらも相当程度の努力をしますが、そちらも相当程度の努力をしてください」
ってことです。

相手の会社を丸ごと変えることはなかなか難しい。でも変えなきゃ新規事業なんか実際のところは無理なんですよね。
ってことは順番に変えていくしかない。一人ひとりを変えていくしかない。
だからまずは目の前の担当者の行動を変える。そこが第一歩だと思うんです。
つまり僕らは「相当程度の努力を一緒にやっていく仲間」という感じ。
いつもより少しだけ頑張ってみよう。一緒だから。
いつもとは違うことに挑戦してみよう。一緒だから。
いつも諦めることを今回は諦めずにいこう。一緒だから。
そんな小さなところから新規事業って始まると思うし、いろんな新規事業は担当者のそういう小さなアクションの上に成り立っていると思うんです。

これって、、、
確かにchat-GPTが言うところの「人の行動変容を促す」ってことだよなあ、と。
で、なんで行動変容を促して新しい挑戦を作りたいかっていうと、、、
挑戦した先には新しい選択肢があるから、なんですよね。
今までと同じことをしていたらAという選択肢しかない。でも、ちょっと行動を変えて挑戦してみたら、Bという選択肢が手に入る。
AとBの中から選ぶことが出来るんです。それって精神的には健全で、つまり健康的ですよね。みたいな。
chat-GPT!
すごいやん!
おしゃれやん!
っていう感じです。
コーポレートサイトの次のリニューアルにそのまま使ってしまいたい気分です笑

真面目な話、、、
「新規事業や新規プロジェクトは作り続けなければいけない」
と、僕はおもっています。
ほとんど強迫観念に近い感覚かもしれません。内(自社)にも外(他社)にも関係なく作りまくらなきゃいけない。
新しいことをやり続けないと成長なんかしないと思うんです。
自分も含めて人を成長させる一番てっとり早い方法は「新しいことを圧倒的な数量でこなしていく」一択。
「量」を追求した先にしか「質」の追求は存在しない。
その「圧倒的な数量」をこなしていく手助けを、こんかいはchat-GPTがやってくれている感じ。
西尾+chat-GPTで作った提案書で先方のエース級が出てくるわけじゃないですか。そこから先の「人vs人」のやり取りをスタッフと一緒に会社が経験していけば、スタッフや会社の成長も早いと思うんですよね。
でもまあ、、、
「『量』を追求した先にしか『質』の追求は存在しない」っていう表現自体がコンプライアンス全盛のこのご時世では社内的にはひょっとしてNGかもしれません苦笑
「量の追求は質の追求に勝る」
「量を追求していたら自然と質も上がる」
って、、、
世代に関係がない言ってみれば「真理」みたいなものだと思うんですけどね〜

ってことを考えていたら見つけた2つの記事が面白かったのでご紹介します^ ^
まず1つ目。
おなじみケヴィン・ケリーさんのAI時代にかんする考察です。
ケヴィンさんは、
◎今後数十年で世界的な人口減少が進み、それに伴いAIやロボットが経済活動の中心的な役割を担うようになる
という持論を展開しています。
面白いのはケヴィンさんが主張するところの「人間が集中すべきこと」の具体的な提示です。
/////
●これまでの歴史では人口は一貫して増加してきたが、近年、出生率の低下が顕著になっている。ほとんどの先進国で合計特殊出生率は2.1を下回り、人口を維持できる水準に達していない。「経済成長はこれまで人口増加と密接に関係していたため、こうした人口減少型の社会は新たな経済モデルを必要とする時代を迎えつつある」というのがケヴィンの主張だ。
●そして彼は、人口減少が進む一方で、数百万のAIやロボットが開発され、社会に導入されていることに注目する。「(人口減少を迎える転換期という)歴史的瞬間に、100万の仮想生命体、10億の人工心、数兆のロボット、そして数十億の作業エージェントが発明されるのは偶然ではない」という大局的な考察をケヴィン・ケリーは展開している。
●さらに彼は「これは生物学的に『生まれたもの』に基づく体制から『作られるもの』ものに基づく体制への移行だ」と彼は語っている。生まれながらの経済は、人間の注意力、人間の欲望、人間の偏見、人間の労働力、人間の態度、人間の消費によって支える一方で、「作られたもの」の経済は、人工的な心、機械の注意力、人工的な労働力、バーチャルなニーズ、製造された欲望によって動かされる。この経済で生産される物質のほとんどは、人間ではなく他の機械によって消費される。
https://kk.org/thetechnium/the-handoff-to-bots/
/////
そしてケヴィン・ケリーさんは、
◎生産性が重要な仕事ならそれは人間がやるべきではない
と主張しています。
生産性が評価基準の仕事はAIや機械にやらせとけ。という感じです。
人間は、芸術、探検、発明、革新、世間話、冒険、交友など、非効率が支配する仕事をすべきだ!とケヴィン・ケリーさんは語っています。
なるほどなあ〜〜〜
ケリーさんが言うようにタスクをAIに労働代替させるスタイルは一部で始まっているんですが、これが一般化するには何十年もの時間を要すると思います。
また、その間に新たな階級闘争や職業が不安定化することによる社会不安なども起きていくはずです。
ケリーさんの言うところの楽観主義。
現実的なこと考えると頭に浮かぶ悲観主義。
この2つが交差しながらどのように進展していくか?楽しみなところであります^ ^

次に2つ目。
僕ん冒頭のおはなしの「世代に関係なく真理的なことってあるよね」っていう部分。
Z世代の次は、
◎α世代(あるふぁ・せだい)
って呼ばれているんですが、、、
どうやらその次の世代が誕生したみたいです笑
α世代の次の世代は、
◎β世代(べーた・せだい)
と言うそうです笑笑笑
『The Wall Street Journal』がわかりやすく説明してくれています。
/////
●2024年1月1日、アルファ世代(Generation Alpha)の後継世代としてベータ世代(Generation Beta)が誕生したが、この『The Wall Street Journal』の記事では、ベータという言葉が意味するネガティブな側面について伝えている。
●ベータ世代という名称を生み出した人口統計者のマーク・マクリンドルはギリシャ文字を用いた世代命名のルールを確立したが、ベータという言葉には「弱い」や「受動的」というスラング的な意味が含まれていることに対してベータ世代の子どもを持つ親から懸念の声が上がっている(逆に「シグマ」はポジティブな意味を持つ)。ベータという言葉がネガティブな意味を持つようになった閉経にはここ数十年間にわたり男性中心主義的なオンライン文化「マノスフィア(manosphere)」の影響がある。そこでは、アルファが、社会的地位が高く、魅力的でリーダーシップのある男性を指す一方で、ベータは、弱く、受動的で、女性に好かれない男性を指すようになった。これにより、「ベータ=劣ったもの」という認識が広まった。
●Z世代や若いミレニアル世代の親の中には、ベータという言葉のネガティブな意味を払拭し、新たらしいポジティブな意味を付与しようとする動きがあることもこの記事では紹介されている。ソフトウェアの世界では、ベータ版とは最新の試作段階の製品をさし、必ずしもネガティブな意味は含んでいないし、むしろ、検証や改善を重ねながら進化していく過程を示している。言語学者のジョン・ケリー は、言葉の意味は時代とともに変わるものであり、いずれ流行が変わる可能性が高いと述べている。
(西尾注:各世代の年齢↓)
X世代
・1965~1980年生まれ
・45~60歳(2025年現在)
ミレニアル世代
・1981~1996年生まれ
・29~44歳(2025年現在)
Z世代
1997~2012年生まれ
・13~28歳(2025年現在)
α世代
・2013~2025年生まれ
・0~12歳(2025年現在)
https://www.wsj.com/lifestyle/a-new-generation-is-here-its-name-is-already-an-insult-23e18a2e
/////
なるほどな〜
X世代=「怠け者世代(Slacker Generation)」
ミレニアル世代=「アボカドトーストを好む浪費家」
z世代=「スノーフレーク世代」
(メンタルが繊細で批判やストレスに弱い世代という意味)
アルファ世代=「iPadキッズ」
として認識されていた、とこの記事では紹介しています。なかなか面白い笑

個人的には、、、
世代のネーミングや特徴づけにも興味はあるといえばあるんですが、言うても、真理的なことは世代が変わろうが変わらないと思うんですよね。
真理的なものが、これらの世代を経由することでどんな文化が生まれていくのか?注目していきたいなあ、と思います。
ぐるっと回って最初の話ですが、、、
行動変容を促すこと。
健康的な選択肢を得ること。
この2つは、人間相手だろうがAI相手だろうが、z世代だろうがα世代だろうが、ずっと変わらない真理のように思います。
今後はAIというとんでもない変数が文化形成に大きな役割を果たしていくことは目に見えています。
新しい文化がこのような真理をどのように解釈していくのか?楽しんでいきたいところですよね^ ^
| カテゴリー | マインドセット |
|---|---|
| タグ |
この記事を書いた人
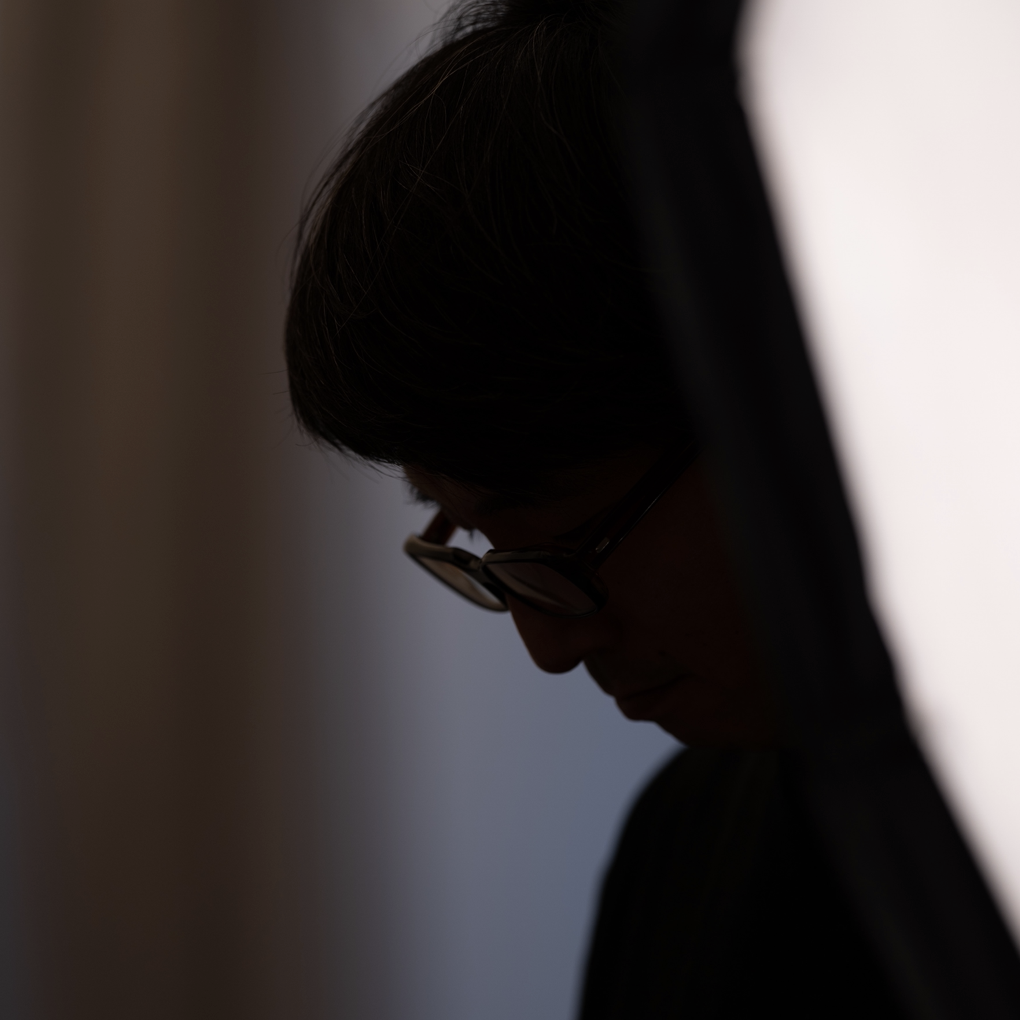
N
株式会社MEETSHOPの取締役。得意なことは整理整頓と言語化。